著者紹介
熊谷徹。
1959年生まれ。
早稲田大学政経学部卒業後、NHKに入局。
90年からはフリージャーナリストとしてドイツ・ミュンヘン市に在住。
欧州の政治、経済、環境問題などについて取材、執筆をしている。
主な著書に、『ドイツ人はなぜ、1年に150日休んでも仕事が回るのか』などがある。
本の概要
ドイツ人の働き方、ライフスタイルについて書かれた本。
ドイツは税金が高いため、平均可処分所得(手取り)は290万円しかない。
しかし、OECD(経済協力開発機構)による調査では、ドイツの生活満足度は日本より高い。(平均値6.5に対して、ドイツ7、日本5.9)
「所得が低いドイツ人は、なぜ日本人より豊かに暮らせるのか?」
「年収が少なくても、豊かに暮らすための生き方」を学べる一冊。
こんな人におすすめ
- お金がなくても、豊かに生きる方法が知りたい
- 仕事はほどほどにして、プライベートな時間を大事にしたい
学びになった点
ドイツ人の倹約法
質素な服装
ドイツ人の服装は日本人に比べると質素だ。女性は男性に比べて身なりに気を遣っているが、多くの男性は無頓着である。彼らがスーツなどを着てきちんとした服装をするのは、就職の面接や顧客とのミーティング、オペラやコンサート鑑賞の時だけだ。
ドイツ人は、日本人ほど服にお金をかけません。
「見た目を気にせず、他人が自分のことをどう見ようが構わない」という人が多いからです。
ドイツのある企業の課長は「スーツ上下は夏用1セット、冬用1セット」を持っているだけだったそうです。
最近ではベンチャー企業だけでなく、大手企業でもポロシャツにジーンズ、スニーカー姿で働いています。
ドイツ人はファッションに無関心のため、衣服代はほとんどかかりません。

ドイツ人の国民性は「ゴーイング・マイ・ウエー」で、他人の目線を気にしないため、服装にはお金をかけないようです。
質素な食事
食事も質素だ。ほとんどのドイツ人は、夕食ではまず火を使った料理をしない。夕食はパンやハム、チーズだけの「アーベンブロート(直訳すると夕方のパン)」と言われる質素な食事で済ませる。パンだけならば夕食は非常に安く済む。
ドイツ人の夕食は、パン・ハム・チーズといった質素なもので済ませます。
ほとんどの家庭は共働きのため、ゆっくり買い物したり調理したりする時間が無いからです。
ドイツで人気の安売りスーパー「アルディ」では、トースト用のパン20枚でたった55セント。
外食も日本人ほど頻繁にしないため、食費は安く済みます。

パンやハムといった、火を使わずそのまま食べれるものなら、時間もお金も節約できます。
プレゼントはしない
ドイツ人は、日本人ほど頻繁に贈り物をしない。旅行から帰ってきた時に同僚や友人にお土産を配る習慣もない。結婚祝いのお返しもしない。多くのドイツ人がプレゼントを贈るのは、彼らにとって最も重要な祭日であるクリスマスと誕生日くらいだ。
ドイツ人は、日本人ほど贈り物をしません。
日本人のようにお中元やお歳暮といった、プレゼントを贈る習慣が無いからです。
ドイツ人がプレゼントを贈るのは、誕生日とクリスマスくらいだと言います。
最近では「毎年プレゼントを贈って、すでに色々な物を持っている」という理由で、クリスマスですら贈り物をやめる家庭も増えているようです。
贈り物をする習慣がないため、日本人ほどプレゼント代はかかりません。

ドイツ人は日本人ほど贈り物をしないため、「もらったからお返ししないと…」と余計な出費が増えることもないです。
娯楽にお金をかけない
ドイツ人は、余暇を過ごすにもあまりお金をかけない。週末や休日には自転車に乗ってサイクリングをしたり、森で散歩をしたり、公園の芝生や河原、自宅のベランダで本を読みながら日光浴をしたりする人が多い。
ドイツ人は、休日もお金をかけずに過ごしています。
- 森で散歩
- 公園で読書
- サイクリング
- 友人を自宅に招いてブランチ(朝食兼昼食)
日本人のように映画館やショッピングなどの「消費活動」で、休みを過ごすことは無いです。
そのため、お金をかけずに余暇活動を楽しむことができています。

私も散歩や読書が趣味なので、ドイツ人の休みの日の過ごし方は共感できます。
自分で出来ることは自分でやる
ドイツ人はまた、「自分でできることは他人の手を借りずに、自分でやる」という原則を持っている。いわゆるDIY(Do it yourself)の精神は彼らのDNAの中に織り込まれている。
ドイツ人は「人の手を借りず、自分でやること」でお金を節約しています。
- 家具の組み立て
- 部屋の壁の塗装
- 浴室のタイル張り
- フローリング張り
- 庭の東屋、池を作る
- 自動車のタイヤ交換
プロ顔負けの本格的な仕事ぶりで、男性・女性問わずDIYに強いそうです。
業者に頼らず自分でやることで、出費を抑えています。

たいていの大工仕事は自分で行うため、家の修繕費・車の修理代といったコストを節約しています。
ドイツの新しい通貨は自由時間
ドイツ人がお金よりも重視しているものが「自由時間」だ。大半のドイツ人は、「プライベートな時間を確保するためには、仕事はほどほどでいい。給料を引き上げるために、家族や友人と過ごす時間を削りたくない」と考えている。
ドイツ人は、お金よりも自由時間を大事にしています。
お金を稼ぐことよりも、家族や友人と過ごすプライベートな時間を優先しているからです。
ドイツ内の1400社で行われたアンケートでは、約19万人が賃上げではなく休暇日数の増加を希望しています。
さらに、週の労働時間を35時間→28時間に減らすことを希望している労働者は、8000人もいたそうです。
これらのデータは、ドイツ人がお金の奴隷になっていないことを表しています。

「お金は大事だけど、自由時間はもっと大事」という価値観は、私も同じです。
ドイツ人と日本人の働き方の違い
有給消化率100%
日独の大きな違いを浮き彫りにするのが、有給休暇の取得率である。旅行会社エクスペディア・ジャパンが2017年12月に発表した調査結果によると、同年の日本の有給休暇取得率は50%。これは、同社が調査した12カ国の中で最低である。
ドイツでは、有給休暇を100%消化するのが常識だといいます。
有給をすべて消化しないと、管理職は組合から「なぜあなたの課には、有給休暇を100%消化しない社員がいるのですか?」と指摘されるからです。
管理職は上司や組合から白い目で見られたくないため、部下に対して有給休暇を100%消化することを義務付けています。
さらに、ドイツでは「連休休暇法」によって、最低24日間の有給休暇が与えられています。
実際には、大半の企業が30日間の有給休暇があるそうです。
日本の法律が定める有給休暇の最低日数は10日間なので、ドイツの1/3しかありません。
つまり、「ドイツの有給消化率は日本の2倍、最低有給日数は日本の3倍ある」ということです。

日本とドイツでは、有給休暇の在り方に大きな差があります。
労働時間は約21%短い
ドイツ人の労働時間は日本人に比べて圧倒的に短い。OECDによると、ドイツの労働者1人あたりの2017年の年間労働時間は1356時間で、日本(1710時間)よりも約21%短い。
ドイツは日本と比べて、圧倒的に労働時間が短いです。
なぜなら、ドイツでは法律によって労働時間が厳しく規制されているからです。
ドイツの労働時間法によると、1日の労働時間は原則8時間超えてはならず、10時間まで延長できるが、他の日の労働時間を短くしなければなりません。
もし毎日10時間を超えて働かせていることが判明した場合、最高1万5000ユーロの罰金があります。
会社によっては、パソコンの画面に「このまま勤務を続けると労働時間が10時間超えます」という警告が出るケースもあるようです。

日本の「働き方改革」は残業時間に上限を設けますが、ドイツの「労働時間法」では1日あたりの労働時間に上限を設けています。
サービス砂漠のドイツ、おもてなし大国の日本
私は毎年日本とドイツを行き来する間に、「日本のおもてなしは客にとっては素晴らしいことだが、サービスを提供する側にとっては、過重な負担になっているのではないか。日本の店員や郵便局員の労働条件は、サービスの手抜きをしているドイツよりも、悪くなっているのではないか」という思いも持つようになってきた。
ドイツは日本と違い、顧客サービスは良くないといいます。
なぜなら、日本のような「過剰サービス」をしていないからです。
たとえば、ドイツの宅配便は細かい時間指定はできず、「配達人が病気で休みだった」という理由で荷物が届かないことがあります。
日本の宅配業者では、14時~16時、16時~18時…のように細かく時間指定できて、必ず荷物が届きます。
しかし、「便利さ」は「忙しさ」の裏返しであり、この「過剰サービス」によって長時間労働・ドライバー不足など、日本の労働条件は悪くなっているのです。
ドイツでは日本のような「過剰サービス」をやめることで、労働者の負担を減らし、ゆとりのある働き方を実現しています。

ドイツではサービスに対する期待度が低いため、サービスが悪くても問題にならないそうです。
年290万円でも豊かな理由
年収が少なくても、自由時間、芸術活動、趣味、自然との触れ合いなどによって「心の豊かさと安定」を得ることは可能である。人間を測る尺度は年収や資産だけではない。心のゆとりや社会への貢献度、周囲の人々との関係も劣らず重要である。
ドイツ人の年収が少なくても、豊かでいられる理由は以下の通りです。
生活にお金はかからない
標準的なドイツ人の生活に、お金はかかりません。
- 食事…パン、ハム、チーズといった質素なもの
- 服装…スーツ上下1着のみで、オシャレに無関心
- 娯楽…散歩、読書、サイクリング、友人と自宅で食事
- 旅行…自動車旅行、ラスト・ミニッツ(激安ツアーパック)、1ヶ所に長期滞在
- 買い物…激安スーパー、蚤の市(フリーマーケット)
- その他…DIYで家の修繕、車の修理など
このように生活コストが低いため、所得が低くても問題なく生活できます。

ドイツ人は無駄な浪費をすることがないため、生活コストが少ないです。
ワークライフバランスが取れている
ドイツ人は日本人と比べて、ワークライフバランスが取れています。
| 日本 | ドイツ | |
| 労働時間 | 1710時間 | 1356時間 |
| 最低有給日数 | 10日 | 24日(30日) |
| 有給消化率 | 50% | 100% |
ドイツ人は日本人より労働時間は短く、休みも多いです。
交替で2~3週間のまとまった休暇を取ることも可能なので、ゆっくり身体を休めることができます。
中には男性社員でも、2~3か月の育児休暇を取る人もいるそうです。
「働くときは働いて、休むときは休む」のように、仕事と休みのバランスが取れているため、年収が少なくても豊かに暮らすことができます。

良い仕事をするためには、しっかり休息をとることが大事です。
ドイツから学ぶ日本の改善点
「日本とドイツの間には法律や文化の違いがあるので、働き方を比べることはできない」という意見もある。しかし、人間の一生が1度しかないということについては、日本人とドイツ人の間に差はない。失われたお金はもう一度稼ぐことができるが、失った時間を取り戻すことはできない。その意味では、「新しい通貨は自由時間だ」というドイツ人の見方には一理ある。
「ドイツ人から学ぶべき、日本の改善点について」私の考えは、以下の通りです。
消費活動からの脱却
日本人は、娯楽を「消費活動」に頼るのをやめたほうがいいと思います。
- 外食など、贅沢な食事
- 新製品、ブランド品のショッピング
- スマホゲームの課金、パチンコなどのギャンブル
お金を使えば使うほど生活コストが上がり、働く時間が増えて自由時間が無くなります。
休みの日はドイツ人のように読書、自然の中を散歩、サイクリングなどをして過ごせば、お金はかかりません。
消費活動をやめることで生活コストは下がり、無理して働く必要は無くなって自由時間は増えるでしょう。

消費活動をやめて「質素」に暮らせば、自分を犠牲にしてまで働く必要は無くなります。
過剰サービスをやめる
日本人の「おもてなし精神」がもたらす「過剰サービス」は、撤廃したほうがいいでしょう。
- 年中無休、24時間営業
- 即日配送、時間指定便
- パン、書籍、お土産の過剰包装
過剰サービスをやめれば、労働者の負担は減ります。
労働者の負担が減れば人件費削減となり、商品やサービスの価格は安くなる。
商品が安くなれば生活コストは下がるので、無理して働く必要は無くなり、自由時間は増えるはずです。
大事なことは「お客様は神様だ」という思想を無くして、サービスへの期待度を下げること。
サービスへの期待度を下げれば、少しくらい配達が遅れたり、スーパーが早く閉まっても、気になりません。

サービスへの期待度を下げることが、過剰サービスを撤廃するための第一歩です。
ワークライフバランスの向上
日本人の多くは「ワークライフバランス」が取れていないため、改善したほうがいいです。
- 労働時間の短縮(1日8時間労働を厳守。残業なし)
- 法律で最低有給日数を増やす(10日から20日へ)
- 有給消化を義務付ける(有給消化率100%を目指す)
お金よりも自由時間を大事にして、ゆとりのある生活をすること。
時間の豊かさが心の豊かさにつながり、生活満足度は上がると思います。

仕事は生活に困らないくらい働いて、自由時間を多く持てば、お金が無くても豊かに暮らせるでしょう。
まとめ
- ドイツ人は人の目を気にしないため、服装にお金をかけない
- ドイツ人の夕食はパン、ハム、チーズといった質素なもので済ませる
- ドイツ人は日本人ほど、頻繁にプレゼントをしない
- ドイツ人の休日は、読書、散歩、サイクリングなどで、お金をかけない
- ドイツ人は「他人の手を借りずに、自分で出来ることは自分でやる」DIY精神を持っている
- ドイツ人は、お金よりも自由時間を大事にしている
- ドイツのサラリーマンは、有給消化率100%が当たり前
- 日本人より、ドイツ人の労働時間は21%低い
- おもてなし大国の日本と比べて、ドイツ人は過剰サービスしない
- ドイツ人の暮らしにお金はかからないため、所得が少なくても問題なく生活できる
- ドイツ人は日本人と比べて休みが多く、ワークライフバランスが取れている
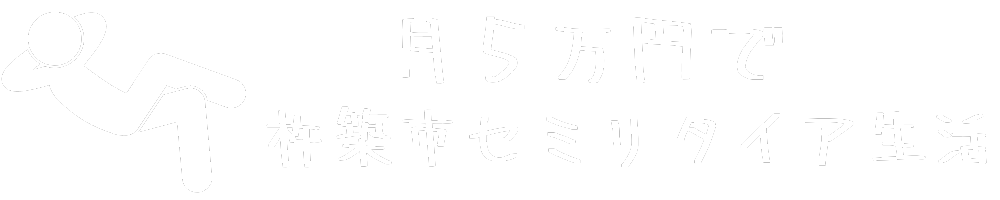




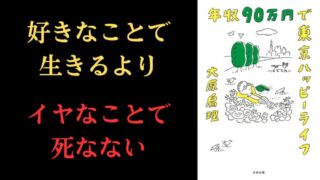
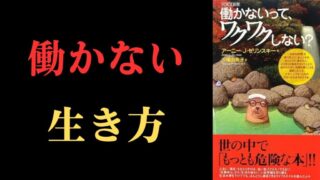
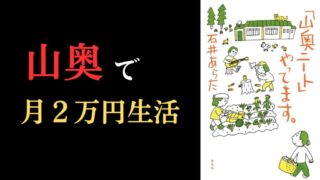
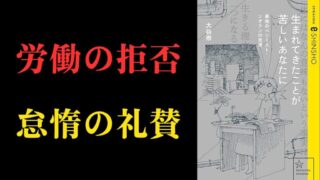


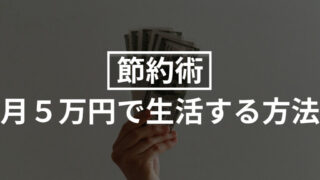


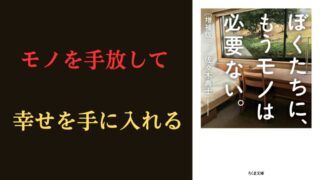
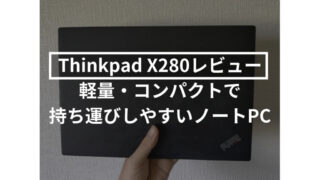

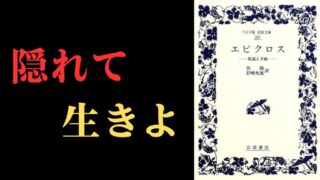
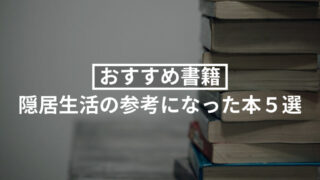

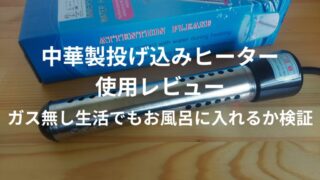
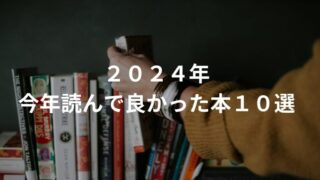
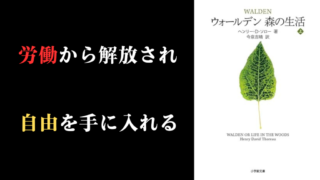
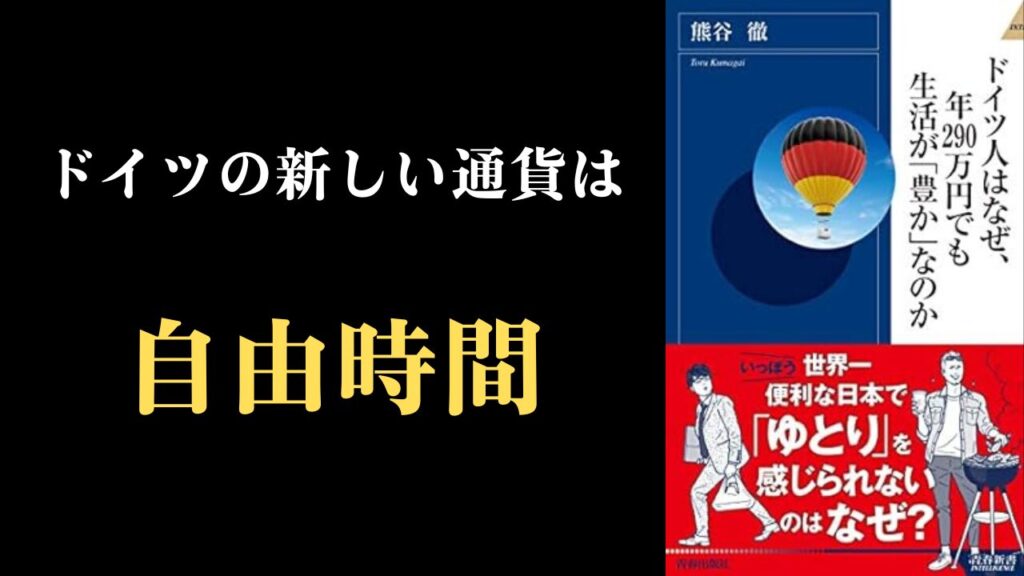



コメント